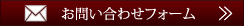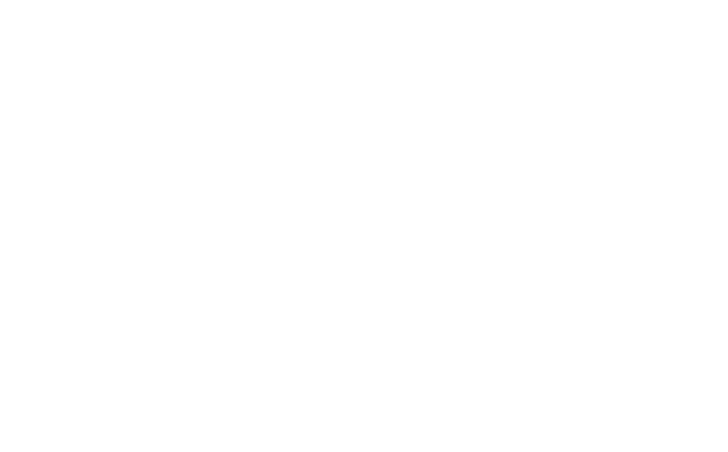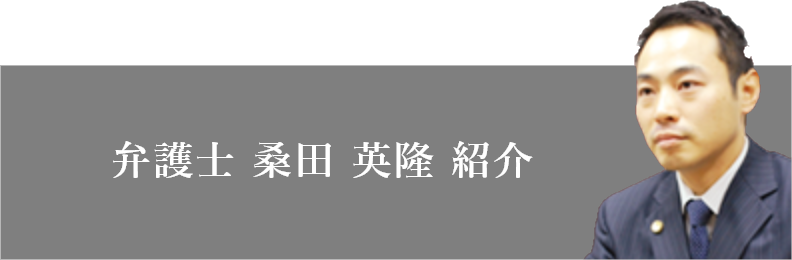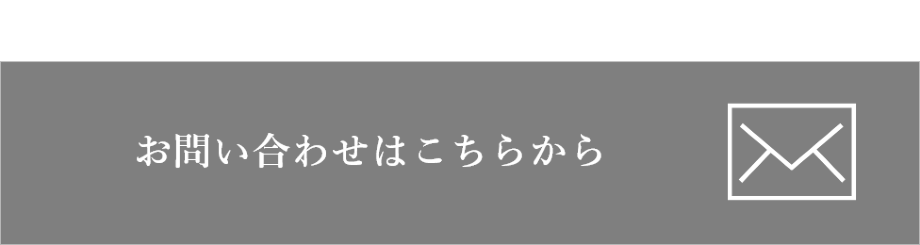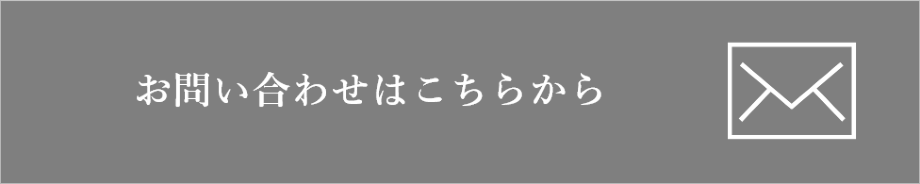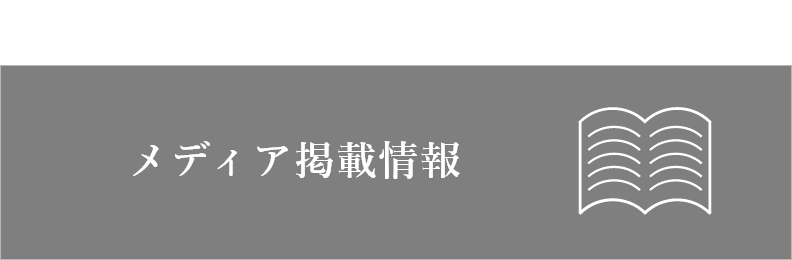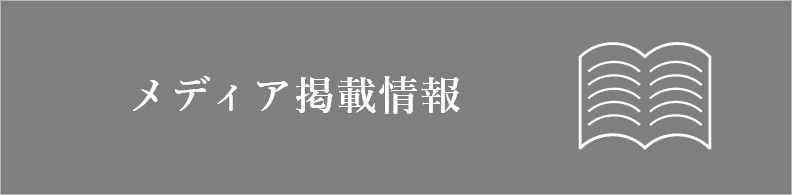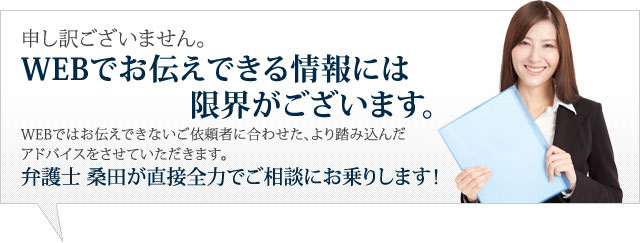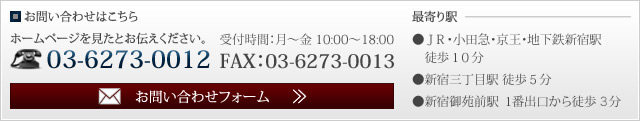弁護士桑田の活動日誌
2024年2月22日 木曜日
議論が迷走する理由
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、法律ではありません。議論の作法、ルールについてお話をしたいと思います。
テレビや居酒屋などで他人の議論を聞いていると、あらぬ方向に議論が迷走し、最後には収拾がつかなくなる場面をよく目にします。
実は、議論には作法やルール、逆に言えば、やってはいけないことがあります。
今回はそのことについてお話しします。
議論が迷走する理由のその1は「検討する場面が共通でない」という場合です。
例えば「絶対に人を殺してはいけないのか」という議論をするときに、一方は「犯罪者に死刑を宣告してよいのか」を念頭に話しているのに、他方は「戦場で襲われそうになった時でも反撃して殺してはいけないのか」を前提にしている場合があります。もちろん、この例は極論で、実際に、ここまでずれていることはないでしょうが。
同じような例として「定義が共通でない」ということもあります。例えば「お客様は絶対に大切か」という問いについて一方は「飲食店でひどいクレームをつける者」も「お客様」として扱い、他方そもそも「ひどいクレームをつける者」は「お客様」には当たらないと考えている場合です(これも極論です、念のため)。
前者であれば「お客様であってもクレーマーは大切ではない」となりますし、後者なら「大切にする人だけお客様になる」ということになります。
このように、検討する場面が共通でなかったり、定義がずれていると、議論は簡単に迷走します。まず「何について議論するのか」の共通認識を持つことが大切です。
次に、議論が迷走する理由のその2は「途中で論点がすり替わる」です。
マンションで管理費を値上げするかどうか、議論する場面を例に挙げます。
値上げを求める側は、例えば、マンションの築年数が長くて設備が老朽化していることや、工事費用が値上がりしていることを理由にします。
一方、値上げしたくない側が「なんで、こんなにひどくなるまで放っておいたのだ。過去の理事会は何をやっていたのか」と言い出したとします。
もしかしたら、過去に、修繕すべき時期に修繕できていなかった例があるのかもしれません。
ですが、過去に遡れない以上、議論すべきは「本当に設備が老朽化しているのか」「工事費用の値上がりを抑えられないのか」「どうしても管理費の値上げが必要か」です。
過去の理事会の不手際は、今、議論する必要性はありません。
ところが、このように途中で論点がどんどん変わって、最後には全然関係ないところで件拡張になっていることがありますが、全くの無意味です。
議論は、論点を明確にし、その論点に対して、双方から意見を言い合うことが大切なのです。
また、議論が迷走する理由その3として「ほかの人もやっている、という反論」があります。
これも良くあります。マンションの廊下にゴミのような私物があふれかえっているので、自分の住戸内にしまうように要請する場合です。
「ほかの人も、傘や三輪車を出しているのに、なんで自分だけ、注意されるのだ」と反論してくるのです。
これは住戸の目的外利用、例えば居住目的しか認められていないマンションで、音楽教室として利用しているような場合にも見られます。
音楽教室としての利用は規約違反だからやめるように申し渡すのに対して「ほかにも事務所や書道教室として使っている」といった反論です。
ですが、ほかの人が規約に違反しているとしてもそれは「ほかの人にも注意するが、だからといってあなたの規約違反が許されるわけではない」という結論になります。
他の人がやっているという言い訳は、とても認められにくいものです。
議論が迷走する理由その4は「逆にあなたはどう思うの」という返答です。
いわゆる、逆質問というものです。議論を投げかけたのに、質問に答えず、質問した側に「あなたはどう思うの」と聞くのでは議論が深まりません。
質問した側も一回は自分の意見を述べるでしょうが、それに反対するのであれば、反対する理由を説明することは最低限のルールです。
最後に、議論が迷走する理由その5ですが「答えをはぐらかす」です。
これは政治家の議論にありがちですが、一方が「どのような対策が必要と考えているのか」と聞いているのに「非常に遺憾であり、あってはならない」などと回答する場合です。
遺憾なのは分かっているので、具体的な対策を聞かせてほしいところです。
このように、議論が迷走する理由はたくさんあります。
お互いが論点をかみ合わせて、具体的に根拠を述べるということが必須だと私は思います。
投稿者 | 記事URL
2024年2月22日 木曜日
立替金を請求するための理由は?
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは立替金の請求です。
皆さんも、自分が払う必要があるわけではありませんが、友達や家族のために一時的に立て替えて支払ったという経験があると思います。
そのような立替金を、友達や家族が払ってくれない場合「返してくれ」となると思います。
では、その場合、法律上の根拠はどのように考えることになるでしょうか。立替金は請求できて当然のことのように思われるかもしれませんが、法律では理屈が必要となります。
考えられるのが、まず「合意」です。つまり、友達から「あとで返すから、食事代立て替えて」と言われて支払ったような場合です。
このような場合は、あらかじめ友達との間で合意が成立しているので、合意に基づく請求が可能となります。
では、例えば、商売をしていて、取引先の代わりに交通費やコピー代、郵送費などを立て替えて支払うということもよくあります。
このような場合も黙示の合意(暗黙の了解)がある場合もあるでしょうが、なんの取り決めもないということもあるでしょう。
こういった場合に立替金を請求する場合の法律上の根拠として考えられるのが「不当利得」です。
不当利得は、一方が法律上の原因なくして利益を得た場合で、他方が損失を被ったときに、損失と因果関係のある利益について、返還請求できるとした民法上の権利です。
また、隣の家の住人が不在の間に台風が来たようなときに、緊急で屋根を修理し、その材料を立て替えて購入したとします。
そのような立替金については「事務管理」という民法の規定を利用して、立替金の支払いを求めることができます。
このように、立替金なら当然に返還請求できるわけではなく、その事案に応じて、合意、不当利得、事務管理といった法律上の根拠があることが前提となります。
もっとも、法律の専門家でないと、どのような場合に、どのような要件で立替金を請求できるかは判断が難しいと思います。
そのようなときには、お気軽に弁護士桑田にご相談ください。懇切丁寧にご対応いたします。
投稿者 | 記事URL
2024年1月31日 水曜日
区分所有法改正の行方6(要綱案について2・建て替えなど)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回は、前回に引き続き、要綱案をもとに、区分所有法改正の方向性について説明します。
今回説明するのは、区分所有建物の再生の円滑化を図る方策、と題された部分です。
今回の改正で、一番注目されているのはこの部分です。というのも、建物再生の円滑化は、建物と所有者の二つの高齢化と呼ばれるマンションの問題への対応策だからです。
もっとも、私は、これまであまり触れてきませんでした。それは、現実のマンションでは、建て替えや取り壊しといった大きな問題よりも、目の前のクレーマー対策などの方が優先度が高いと考えたからです。
とはいえ、築年数が40年を超えるマンションもこれからどんどん増えていきます。なので、建て替えなども避けて通れなくなることは明らかです。
そこで、今回、改正法の中で、建て替えなどに関係する部分を説明することにしました。
マンションの建て替えについて、現行法は、区分所有者及びその議決権の5分の4以上の賛成が必要としています。
しかし、要件が厳格であるためになかなか成立しないことに問題点がありました。
そこで、一定の場合には、区分所有者及びその議決権の4分の3以上の賛成、と要件を緩和することにしました。
一定の場合というのは、地震や火災に対する安全性に問題がある場合、外壁等が剥離し落下等のおそれがある場合、配管設備の劣化が著しい場合、高齢者等への対応に問題がある場合なです。
その他に、建物と敷地を一括して売却する場合、建物を取り壊して敷地を売却する場合、建物を取り壊す場合、建物が全部滅失した敷地に建物を再度建築する場合、敷地を売却する場合などについて、手続が検討されています。
区分所有法の改正は大変幅が広く、全部を理解することは困難と思われます。
私は、改正区分所有法の講義の開催も検討していますので、興味のある管理組合、理事会、管理会社の方はお気軽にご連絡ください。
投稿者 | 記事URL
2024年1月31日 水曜日
区分所有法改正の行方5(要綱案について1)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
これまで、区分所有法の改正について、4回にわたり、法務省の中間試案をもとに解説しました。
法律の改正は、中間試案から議論が進められ要綱が示され、最終的には改正した法律が成立するという流れになります。
近時、この要綱の案が出されましたが、概ね、中間試案に沿った提案がされ、内容を深められていったようです。
今回は、要綱案が出たことを踏まえ、これまでに触れられていなかった改正について、重要な個所を説明したいと思います。
まず、総会の決議についての改正が考えられています。
要綱案には、現行法の多数決割合を維持しながら、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決する、とあります。
規約改正を例に挙げると、4分の3の賛成が必要という割合は変わりませんが、その対象は組合員総数ではなく、出席した組合員数とするという扱いと思われます。
これまでは、マンションの維持管理に無関心で、出席もしないし、賛否の意思表示もしない組合員は、事実上、反対と同じ扱いでした。
そのため、本来必要な規約の改正なのに、特別決議に必要な4分の3の賛成を得られずに成立しなかった例は数多く見受けられます。
改正法によって、こうした事態を回避できる可能性が出てきました。
また、共用部分の変更については、さらに、一定の場合には「出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上」と、要件がさらに緩和されています。
どのような場合かというと、共用部分の設置や保存に瑕疵があることで他人の権利等が侵害される場合の瑕疵の除去、高齢者等の負担軽減のための変更です。
これらの場合については、規約で、頭数だけでなく議決権数も過半数まで減じることができる、とされています。
共用部分の欠陥の除去や高齢者の身体の負担を軽くするような変更は、できるだけ要件を緩和しようという考え方です。
長くなりましたので、次回に譲りますが、その他に、建て替え決議の要件の変更など、建物と所有者の二つの高齢化と呼ばれる問題に対応した改正が予定されています。
2024年2月頃には要綱が出される予定ですので、それを待って、より詳しい説明をいたします。
とはいえ、区分所有法改正は多岐にわたり、専門用語も多いことから、理解が大変だと思います。
私は、改正区分所有法の講義も行う予定をしていますので、興味のある管理組合、理事会、管理会社の方はお気軽にご連絡ください。
投稿者 | 記事URL
2023年10月3日 火曜日
リゾートマンションの法律トラブル
皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、リゾートマンションの法律トラブルについてです。
私はリゾートマンションの法律顧問もしております。そのマンションは理事会が熱心に活動していますが、リゾートマンションの中には管理が行き届いていないものも少なくありません。
私が相談を受けた地方のリゾートマンションも、多くの問題を抱えていました。
皆様は、リゾートマンションをご存じでしょうか。リゾートマンションは、主に観光地や景勝地などに建てられ、別荘の代わりとして使われることが想定されたマンションです。
ですので、区分所有者の方も、年に数回程度しか訪れないことが多いでしょう。そのため、区分所有者の方の、マンションの維持管理に対する関心が低くなりがち、という傾向はあります。
そうなると、高経年のリゾートマンションになってくると、管理費が長期間滞納される、管理費が理事長等によって横領される、住戸内の維持管理ができていない、共用部分の維持管理もなおざり、といったトラブルが多発することになります。
リゾートマンションの多くは、いわゆるバブル時代に建てられた豪華なものが多いので、現在、建築から30年前後となり、問題が発生しやすい状況になっています。
また、最近では、新築当初に購入された方が定年を迎え、リゾートマンションで生活する傾向も出てきています。そうなると、居住者と、別荘として利用する方との意識の相違からトラブルとなる例もあるようです。
では、このようなトラブルに対してはどのような対策が取れるでしょうか。
まずは、住民の方の意識が高まらないと話が進みません。何十年も総会も開催されず、理事長もいない、では解決が困難になります。
このような場合には、区分所有者の有志で管理組合創設のための総会の開催を計画することから始めるしかありません。
一方、一応、管理組合や理事会が機能しているのであれば、個別の問題については、調査し、一つずつ対処していくことになるでしょう。
例えば、管理費の滞納であれば、理事会から督促し、それでも支払わなければ、時効にかからないよう提訴して回収を図る必要があります。
また、 横領事案であれば、預金口座の流れなどを精査して証拠を集めることからのスタートとなるでしょう。
住戸や共用部分の管理不全については、区分所有法の改正について書かれた記事で詳しく説明していますが、改正後は、管理不全専有部分管理制度や管理不全共用部分管理制度を利用することが有効な場合があります。
ですが、どのような問題であっても、法律家ではない一般の管理組合、理事会の方では、どこから手を付ければよいか、判断しがたいところもあるでしょう。
特にリゾートマンションのような特殊なマンションでは容易に解決しないことが予想されます。
そのようなときは、弁護士桑田までご連絡ください。
リゾートマンションでの経験も踏まえて、アドバイスを差し上げたいと思います。
投稿者 | 記事URL
2023年9月29日 金曜日
区分所有法改正の行方4(外国人所有者への対応)
皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマも、前回に引き続き、区分所有法の改正についてです。
今回は、外国人の所有者や日本人でも国外で生活しているなど、国内に住所を有していない所有者への対応についてです。
マンションの住戸を、自分が住むためではなく、賃貸に出すために所有している方は、以前からたくさんいました。
そして、近年では、外国人投資家が投資用に住戸を購入する例や、日本人の所有者であっても海外で勤務している例が増えており、連絡を取ることが困難なケースも少なくありません。
そのような場合、例えば、配管工事のための立入りの同意を得られない、管理費等を滞納しているが督促できない、総会の招集通知を送付できない、総会に出席したり議決権行使書を出すなどの対応がされないために定足数や特別決議の要件の充足に支障をきたす、といった、数々のトラブルが発生しかねません。
実際、私のもとにも、外国人区分所有者関係の相談がかなり多く寄せられています。
そこで、改正法では、区分所有者が国外にいる場合に国内管理人を選任することができるとする制度を新設することが提案されています。
そして、国内管理人を選任した場合には、管理組合への報告をしなければならないことになります。
国内管理人は、立入りの同意をする、管理費等の支払事務を行う、招集通知を受領する、議決権を行使するなどの権限が認められ、トラブル予防のために有益と思われます。
もっとも、国内管理人の選任は、区分所有者が任意に行うこととされていますので、区分所有者にその意思がなければ選任されません。
別案として、国内管理人の義務付けを行う案も出されていますが、その義務に違反した場合にどのような効果があるのかなどの課題が多いという指摘がされています。
いずれにしても、今後、制度の詳細を詰めていくことと思われますので、経緯を見守る必要があります。
外国人所有者や海外在住の日本人の区分所有者に対するトラブルがありましたら、弁護士桑田までお問い合わせください。
懇切丁寧にご対応させていただきます。
投稿者 | 記事URL
2023年9月21日 木曜日
区分所有法改正の行方その3(ゴミ屋敷、ゴミ放置)
皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回も前回に引き続き、2024年に予定されている区分所有法の改正についてです。
前回は区分所有者が行方不明になったことによるデメリットへの対策を説明しました。今回は「区分所有者は住戸で生活しているが、その居住者の管理が悪く、ゴミ屋敷化していたり、住戸の前の廊下にゴミを放置したような場合」への対応です。
まずは、住戸内の管理に問題がある場合への対策として、管理不全専有部分管理制度の新設が予定されています。他の居住者や管理組合法人などが、裁判所に管理不全専有部分管理命令の発令を申し立て、認められれば管理不全専有部分管理命令が発令されます。
発令の要件は「区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害される恐れがある場合において、必要があるとき」です。どの程度に至れば要件に該当するのかは、事例を積み重ねる必要があります。
申立てが認められれば、管理不全専有部分管理人が選任され、ゴミの撤去などができるようになります。
次に、住戸前の廊下などに私物が放置されるなど共用部分の管理が不全な場合ですが、この場合に用意された制度が、管理不全共用部分管理制度です。管理不全専有部分管理制度同様、利害関係人が申し立て、認められれば管理不全共用部分管理人が選任され、住戸前の廊下に放置されているゴミを撤去できるようになります。
利害関係人は、主にマンション外の近隣住民が想定されていますが、他の組合員による利用もありうるとされているようです。
なお、典型例が「ゴミ関連」ですので、例示していますが、もちろん、ゴミに限らず、居住者による住戸や廊下などの共用部分の管理が悪い場合は広く対象となります。
これまでも、廊下にゴミを放置した居住者に対しては使用細則違反などで提訴して撤去を求めてきましたが、勝訴しても居住者が判決に従わないとさらに解決に時間を要するという問題がありました。ですが、管理不全共用部分管理人が選任されれば、放置したゴミを処分するなどの対応が可能になり、迅速な解決ができるようになるという利点があります。
このように区分所有法の改正によってさまざまな制度が用意されることが予想されます。
とはいえ、一般の理事長や理事の皆様には、専門的な法律の理解や手続を実行することは困難と思われます。
そのようなときは、弁護士桑田にお気軽にお声がけください。
丁寧に対応いたします。
投稿者 | 記事URL
2023年9月6日 水曜日
区分所有法改正の行方その2(所在不明組合員の扱い)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、区分所有法改正の行方の第2回として、組合員の所在が不明となった場合の扱いについて説明します。
以前、私もこのブログの中で「所在不明の区分所有者への管理組合の対応」という記事を掲載しましたが、当時から、所在不明者問題が世の中に浸透し、議論が進みました。
改正において想定しているのは、所在不明の組合員と総会との関係及び所在不明組合員の専有部分等の管理です。
まず、総会との関係ですが、特に特別決議など議案の成立要件が厳格な場合、所在不明の組合員がいることによって賛成議決権数が足りず、成立が見込めなかったり、そもそもの定足数にさえ至らない場合があります。総会の招集通知や議案書を送ること自体ができないということも予想されます。
そこで、組合員が行方不明である場合に、裁判所に対して「所在等不明区分所有者の除外決定」を申し立て、認められた場合には、行方不明の組合員及びその議決権を総会の決議から除外することができるという制度が提案されています。この申立てが認められた場合には、行方不明の組合員宛の招集通知の発送は不要となります。
法務省の中間試案の補足説明によると、具体的な申立ての方法などについては検討中のようです。
次に、組合員の専有部分等の管理との関係ですが、組合員が行方不明になると専有部分を適切に維持管理することが期待できなくなります。そして、その管理不全は共用部分にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
このような場合、先ほど挙げたブログのように、従前から、不在者財産管理人制度はありました。
ですが、不在者財産管理人は、「不在者」という人を基準にしているため、その管理も不在者の財産全般に及びます。そのため、管理人の費用も高額になりますし、選任の手続にも時間を要していました。
一方、令和5年4月1日に施行された改正民法では「所有者不明建物管理命令」という制度が新設されました。この制度は、建物が対象ですので、管理人の費用がより減額されたり、選任までの時間も短縮されるのではないかと想定されます。もっとも、区分所有法は、民法の「所有者不明建物管理命令」の適用を除外しているため、マンションではこの制度は使えませんでした。
そこで、マンションについても新たに「所有者不明専有部分管理命令」という制度が設けられました。この制度も費用が減額されたり選任が早期にされることも期待できるのではないかと考えています。
その内容は、おおよそ民法上の制度と同じであり、裁判所に申し立て、命令が出されたら、所有者不明専有部分管理人が選任され、専有部分等の管理がなされることになります。また、その効力は、共用部分や付属施設などにも及び、例えば、管理組合の総会において、所有者の代わりに議決権を行使することも原則として可能です。
なお、所有者が住んでいても住戸の中がゴミ屋敷状態になっていたり、排水管の清掃が拒否されて住戸内の配管が腐食しているということがあります。また、住戸の前の廊下に悪臭を放つゴミを放置しているケースもあります。それらについては、管理不全専有部分管理制度と管理不全共用部分管理制度という二つの制度が新設される予定です。こちらについては、別の記事で紹介します。
このように区分所有法の改正においては、所在不明の組合員への対策が設けられました。
実際にどのような改正となるかは未確定ですが、このような対策が設けられた場合には、多くの管理組合で制度を利用することが考えられます。
もっとも、一般の理事の方や管理会社の方では申し立てなどの方法がわかりにくいと思います。
申立てを希望される場合には、当職にお気軽にご相談ください。懇切丁寧に対応させていただきます。
投稿者 | 記事URL
2023年9月5日 火曜日
区分所有法改正の行方その1(改正の流れ)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、区分所有法の改正についてです。
個別の論点に入る前に、まず、区分所有法の改正の大まかな流れを見ていきたいと思います。
区分所有法に限らず、法律は技術革新や国民の意識の変化に合わせて、その都度、改正が図られます。例えば、離婚後の未成年の子の親権者は父母のどちらかですが、家族法の改正では、共同親権の導入も検討されています。これも、離婚後も子の養育に関わっていたいという両親が増えてきたことの反映でしょう。ただし、多様な意見があり、共同親権が実際に導入されるかは不明です。
区分所有法に話を戻しますと、今回の改正は、主に区分所有建物管理の円滑化、区分所有建物の再生の円滑化、被災区分所有建物の再生の円滑化がテーマとなっています。
2024年の通常国会での改正案の提出を目指すとのことです。通常国会は、1月中旬に始まり、6月に終わりますので、来年の今頃は改正区分所有法が成立しているかもしれません。
改正の内容は広範にわたっていますが、「再生の円滑化」というのは、主として建て替えに関する要件などの検討が対象となっています。
改正に先立って、法務省から区分所有法改正の中間試案が出されました。
次回以降のブログでは、中間試案をもとに主に「区分所有建物管理の円滑化」について説明していきます。
具体的には、所在不明の区分所有者の扱い、特別決議の多数決要件の緩和、専有部分の管理が不全な場合の対応策、区分所有者が国外にいる場合の対応などです。
これらは、居住者の行方不明、専有部分のゴミ屋敷化、外国人の区分所有者のトラブルなど、理事会や管理会社が大変苦労されてきたところであり、改正の行方はしっかり追っていきたいと思います。
もっとも、一般の理事の方には、ブログを読んでもわからないという方もいらっしゃると思います。
区分所有法については、当職も講演や講義を行うこともできます。
区分所有法の講演や、理事会での簡単な勉強会などをご希望される場合は、いつでもお声がけください。
投稿者 | 記事URL
2023年8月29日 火曜日
クレーマー住民への具体的対処法(大規模修繕拒否篇)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、クレーマー住民が大規模修繕への協力を拒否した場合の対応です。
クレーマー住民の中には「工事費用が高い」「理事長が工事会社からキックバックを受け取っている」など、様々な理由で大規模修繕に反対することがしばしばあります。
理事会としては、相見積をとって、真剣に検討して工事会社も選定しているのに、勝手な憶測で工事への協力を拒否されては、不満が募るのも当然のことでしょう。
クレーマー住民の拒否のやり方は、以下のようなパターンがあります。
①大規模修繕を検討する理事会の妨害
②大規模修繕を決議する総会で大声で自分の個人的な感情を怒鳴り散らす
③クレーマー住民の所有する住戸の中を抜けてバルコニーを至らないと工事できないのに、住戸への立入りを認めない
④工事そのものも直接妨害する
①については以前掲載しましたこちらの記事(理事会でのクレーマー対応)を、②についても以前掲載したこちらの記事(総会時のクレーマー対応)を、ご参考にしてください。
③についてはこちらの記事(クレーマーの立入り拒否対応)と同様の対応になりますので、そちらを参照ください。
残るのは④です。工事そのものを物理的に、どうしても妨害しようとするクレーマー住民がいることも否定できません。
このような場合には、理事会や管理会社が説得に乗り出しますが、どうしても納得しないことがあります。
そういった場合には、工事妨害禁止の裁判を起こすことになりますし、妨害が予想される場合には工事妨害禁止の仮処分を求めることが必要になります。
といっても、工事妨害禁止の裁判や仮処分を行うには区分所有法や民事訴訟法の専門的な知識が必要であり、一般の理事会や管理会社での対応は困難と思います。
そのような場合には弁護士桑田までお気軽にご相談ください。
丁寧にご説明いたします。
なお、管理規約の中で、規約や細則に違反した組合員に対して、弁護士費用を請求できると規定されている例は多いと思います。
その場合には、弁護士費用もクレーマー住民に請求することで、他の組合員の方に弁護士費用を負担させずに済むことも多々ありますので、合わせてご相談ください。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (6)
- 2023年7月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2022年6月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (3)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (3)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (6)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (2)
- 2015年12月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年1月 (2)
- 2014年6月 (2)
- 2014年3月 (3)
- 2014年1月 (2)
- 2013年7月 (1)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (2)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (2)
- 2012年7月 (13)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (3)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (2)