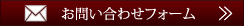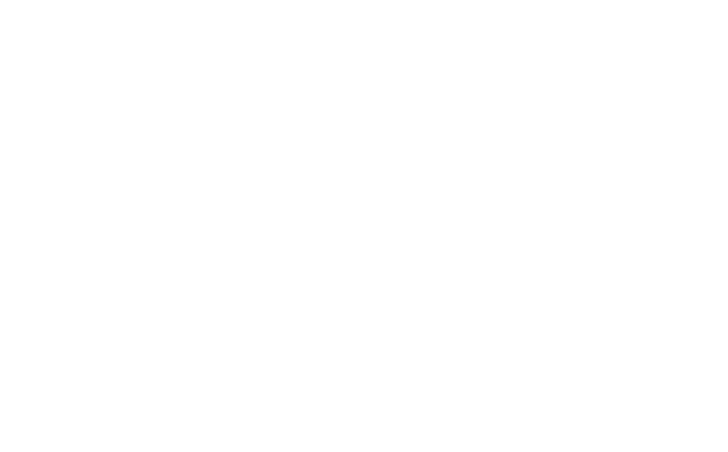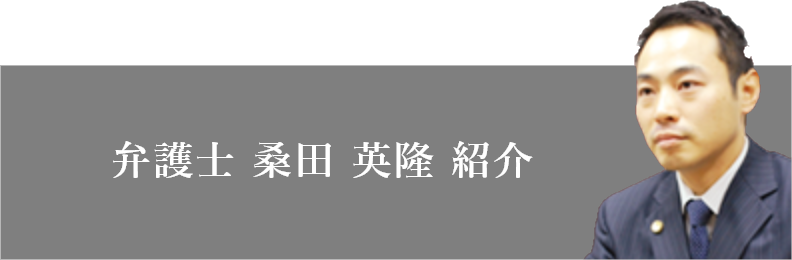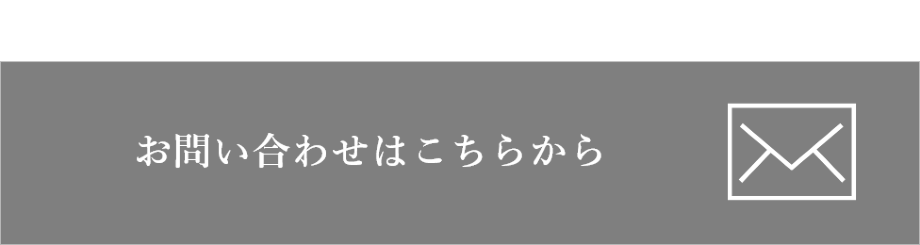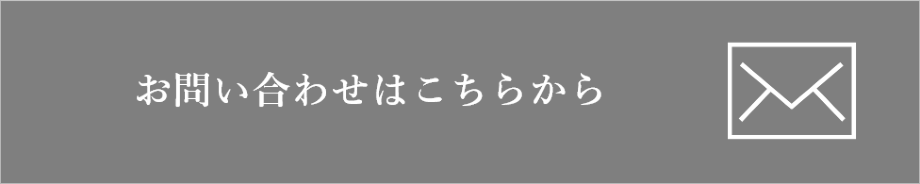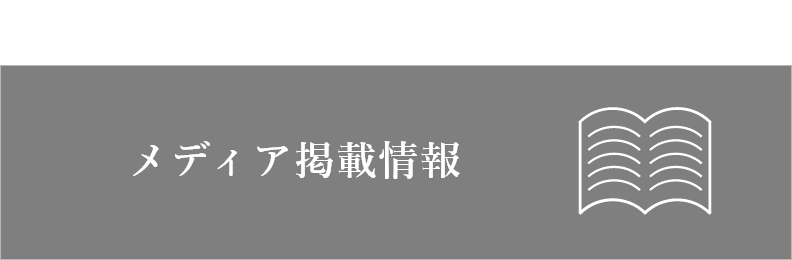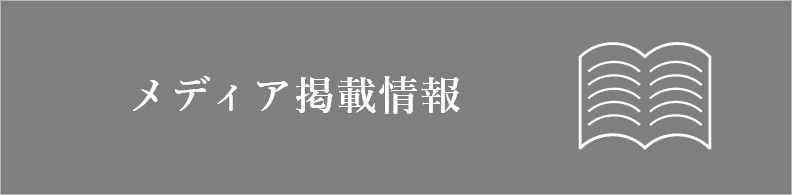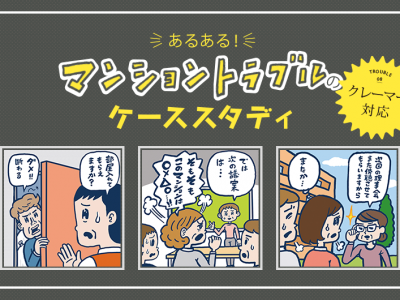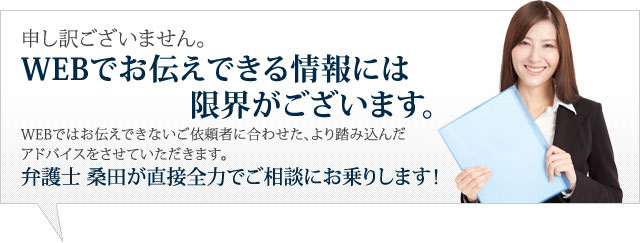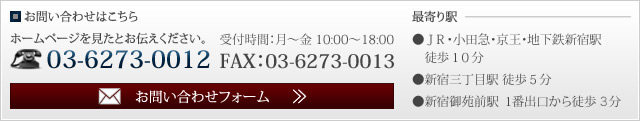弁護士桑田の活動日誌
2020年11月19日 木曜日
トラブルメーカーへの対応と標準管理規約の態様
皆様,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンション内のトラブルメーカーへの対応の仕方について,標準管理規約にどのように記載されているか,です。
特に今回は,標準管理規約66条と67条3項の関係について,説明したいと思います。
66条には,区分所有者や占有者がいわゆる共同利益背反行為を行った場合などに,他の区分所有者全員は,その行為の停止,専有部分の使用禁止など,法的措置を含めた一定の請求ができることを規定しています。
区分所有法57条から60条までを確認する規定です。
67条には,1項2項で法令や規約に違反した場合などに,理事長が是正勧告,指示,警告できることなどが規定され,3項で,理事長が法令などに違反した行為の差止など必要な法的措置ができることを規定しています。
つまり,66条も67条3項も,マンション内のトラブルメーカーに対する管理組合側の法的な措置を定めているのです。
では,どこにどのような違いがあるのでしょうか。
まず,対象となる者が違います。66条は区分所有者と占有者のみが対象ですが,67条は区分所有者,占有者のほかそれらの同居人も含まれます。
次に,行為の対象が違います。66条は共同利益背反行為が対象となっていますが,管理規約や細則に違反しても必ずしも共同利益背反行為には該当しません。ですが,67条3項は規約や細則の違反,敷地や共用部分での不法行為などもその対象としています。
また,手続も違います。66条では裁判を起こすのにその都度総会決議が必要ですが,67条の場合は総会決議が必要でなく理事会決議で足ります。もっとも,訴訟提起の公平性から,67条による場合も総会決議を経ておくことが望ましいでしょう。
このように,67条3項は66条より広範な内容を規定し,不適切なトラブルメーカーの行動に対し,より広く法的な対応ができるようにしています。
もっとも,実際に訴訟を提起するとした場合,総会でどのような議決を得ればよいのか,また,どのように手続を進めればよいのかは一般の方には容易には判断できないと思います。
お困りの際には弁護士桑田までお気軽にご相談ください。
どのような方法がベストか,一緒に考えていきたいと思います。
投稿者 | 記事URL
2020年10月21日 水曜日
遺言,遺産分割協議書の偽造
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,遺言や遺産分割協議書が偽造された場合の対応です。
皆さんは,遺言や遺産分割協議書が偽造されることはめったにない,と思われているのではないでしょうか。
確かに頻繁に起こることではありませんが,私は,遺言の偽造事件も,遺産分割協議書の偽造事件も扱ったことがあります。
当然,相手方は偽造したことを素直には認めません。そのため,準備や対策が必要となります。
私が過去に扱った遺言の偽造事件は,兄弟の一人が親の遺言を偽造し,別の兄弟が遺言無効を主張していた事案です。
第一審では別の弁護士が原告の代理人でしたが,遺言は偽造でないと判断されてしまい,納得できない原告が控訴し,私が新たに控訴審の代理人を担当しました。
偽造かどうかを判断するには,筆跡鑑定のほか,遺言が作成されたとされる当時の状況つまり作成場所,作成時間,作成時に誰が遺言者の近くにいたのか,作成の方法,遺言の内容などをもとに遺言作成状況の合理性を慎重に検討することになります。
第一審でも筆跡は問題となり鑑定も行われていましたが,親は高齢で利き手の右手が不自由になり,遺言書を書いたとしたら左手しかなかったにもかかわらず,第一審ではそのような事情は明らかにならないまま,遺言の筆跡が過去の遺言者の筆跡と似ている似ていないといった議論に終始していました。
そこで,私は,それらの議論では今回の偽造は判断できないことを主張した上で,作成場所である病院の看護日誌から作成日には遺言に立ち会ったと主張するされる相手方が来院しているはずがないこと,病院の図面をもとに看護士らに見られずに相手方が病室に入ることは不可能であることなどを主張しました。
その結果,遺言書の作成についての相手方の説明は不自然であることが浮き彫りになり,当方に有利な和解を行うことができました。
もう一つは,兄が,妹との遺産分割協議書を偽造し,その遺産分割協議書を利用して,死亡した親の所有する土地建物等を売却してしまったという事例です。
私は,妹の代理人として,損害賠償請求をしました。
偽造が判明した経緯は,親の所有していた建物の取壊しが行われたことに妹が気づいたことです。
妹から相談を受けた私が法務局にて遺産分割協議書を閲覧したところ,全く妹の身に覚えのない協議書が出てきました。
協議書の妹の氏名の筆跡は兄嫁ではないかということで,兄嫁の筆跡のある書類を徹底的に探し出し,比較対照して,協議書の筆跡が兄嫁で間違いないと確認しました。
遺産分割協議書の作成には実印が必要ですが,妹には印鑑登録をした覚えはないとのことでした。ですが,兄から「親の保険の解約に必要」と言われ,住基カードを渡したことがあるとのことでした。
そのため,住基カードを利用して妹名義の印鑑登録を無断で行い遺産分割協議書に押印したと判断しました。
訴訟でも偽造が激しく争われると予想しましたが,相手方代理人は偽造を争うことが困難と判断し,最初から偽造を認めてきました。
その結果,兄が妹に相当額の支払いをすることで和解して解決しました。
このように,遺言や遺産分割協議書の偽造の立証は簡単ではありませんが,詳細な検討を加えることで立証に至ることが可能なのです。
もっとも,このような作業は一般の方には困難と思われますので,偽造のトラブルに巻き込まれた際には,当職にご連絡ください。
丁寧に対応させていただきます。
投稿者 | 記事URL
2020年10月13日 火曜日
賃借人が自殺したときの賃貸人(大家さん)の対応
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,賃借人が物件の中で自殺してしまった場合の賃貸人の法的対応についてです。
賃借人が自殺してしまった場合,賃貸人としては,様々な問題に直面することになります。
残置物をどう処理するか。また,自殺の仕方によっては,原状回復費用が発生することもあります。
例えば,裁判例の中では,お風呂の中で自殺した場合にユニットバスそのものを交換した例があります。
広範囲に付着した血のりの除去が必要なこともあります。
自殺される賃借人は経済的に困窮している方も多く,賃料の滞納が発生している例もあるでしょう。
そして,なんといっても,最大の問題は,その物件が事故物件扱いとなり,借り手がつかないとか,賃料が減額されることです。
このような将来得られたはずなのに得られない利益を逸失利益と言います。
では,これらのトラブルに対して,賃貸人はどのように対応することになるのでしょうか。
まず,行うのは賃借人の相続人を調査することです。残置物は,相続人に引き取ってもらうことになります。
次に,逸失利益,原状回復費用,滞納賃料等の請求は,誰に対してどのように行うのでしょうか。
その前提として,賃借人は,一般に善管注意義務の一環として,物件内で自殺しないようにする義務もあります。
賃借人はこの義務に違反しているので,賃貸人は債務不履行に基づく損害賠償請求が可能となります。
そして,賃借人は死亡しているので,その相続人又は保証人にこれらの損害賠償を請求することになります。
ただし,相続人が相続放棄してしまっている可能性もあることに注意して下さい。
では,逸失利益はいくらになるのでしょうか。
近時の裁判例をいくつか確認したところ,都心で交通の便が良く流動性が高い物件との前提ですが,おおむね「1年間は借り手がつかず賃料不発生,その後2年間は賃料半額」と評価しているようでした。
もっとも,将来の賃料をを現在一括しての支払いを請求することから,中間利息を控除する扱いになります。
中間利息の控除についての説明は割愛しますが,3年程度ですと,おおよそ9掛けくらいです。
例えば,家賃が10万円とすると1年分で120万円,2年目と3年目が半額なので合わせて120万円,合計240万円を回収できない賃料と評価し,これに9掛けして,約216万円が逸失利益として認められます。
そこに原状回復費用などを足して損害額を計算することになります。
もっとも,相続人を調査したり,これらの請求を行うことは賃貸人にとっては大変な作業と思いますので,当職にお気軽にご相談ください。
投稿者 | 記事URL
2020年10月5日 月曜日
委任状,出席票,議決権行使書の開示要求への対応
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,理事会が,組合員から,マンションの総会の委任状,出席票,議決権行使書などの開示(閲覧)を求められた場合の対応についてです。
理事会としては適切に集計し,誤りなく議決の承認不承認を確認していたとしても,組合員の中には集計に納得せず,委任状などを開示するよう求める組合員もいますが,このような要求があった場合に,理事会は開示して閲覧させなければならないのでしょうか。
なお,このような前提ですので,提出した本人が開示を求める場合を想定しているものではありません。
このような場合,開示を求める組合員の理由付けはおおよそ次のようなものになります。
管理規約では組合員は総会の議事録を閲覧できるところ,委任状等も総会議事録と一体をなす文書だから,委任状等も閲覧できるというものです。
これに対して,委任状,出席票について,東京地裁平成26年9月18日判決は,対象となるマンションの管理規約が,委任状が議事録とは別の書面であることを前提に委任について規定しているのに委任状を閲覧できる旨の定めを置いていないから,この管理規約においては委任状の閲覧を求める権利を組合員に認めていない旨の判示をして,組合員による閲覧を認めませんでした。
この管理規約は一般的な内容と思われますし,議決権行使書についても閲覧できる旨の定めがないのが通常でしょうから,この裁判例によれば,理事会は,委任状などの開示や閲覧の要求を拒否することも不相当とはならないのではないかと思われます。
投稿者 | 記事URL
2020年8月31日 月曜日
弁護士による管理組合総会のサポート
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,管理組合の総会に対する弁護士からのサポートについてです。
顧問弁護士であれば,当然,総会に出席するなどの支援を行います。
それとは別に,最近,管理組合から,単発の総会をサポートして欲しい,といった相談を複数受けました。
例えば,管理組合内部で感情的な対立が激しく理事会がいわれのない批判を受けている,管理会社が非協力的である,組合員からの総会招集の要求を受けて開催せざるを得ないなどの特殊な場合です。
このような場合は,招集期間の確保,議長の選任,説明義務違反にならないように議案を説明する方法,決議を正確に行うなど,
総会決議無効の裁判を起こされても敗訴しないよう,手続を慎重に進める必要があります。
このような場合は,やはり専門的な知識を有する弁護士による総会手続のサポートが大変重要になります。
例えば,招集期間は通常2週間とされていますが,起点は通知を発信した日であって,組合員の手元に届いた日ではありません。
また,「2週間」は発信した日と開催日の間に2週間が必要ということであり,発信した日と開催日を含めてはいけません。
こういったことは,知らないとどうしようもないことなのです。
そこで,私も,特定の総会のみのサポートを行うことがあります。
招集通知の書き方,議案書の書き方,委任状や議決権行使書の書き方,スケジュールの組み方などを検討し,総会のシナリオや想定問答集も準備します。
必要とあれば,総会に出席することもあります。
特殊な総会を開かなければならないときにはぜひ,弁護士桑田にご相談ください。
理事会の皆様と一緒に,総会の成功をサポートしたいと思います。
投稿者 | 記事URL
2020年6月22日 月曜日
分譲マンションに関係する法律
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,分譲マンションに関係する法律のご紹介です。なお、正式名称は長いため、略称での紹介となります。
分譲マンションには,共用部分,専有部分などがあり,特殊な権利関係が発生します。
そのため,分譲マンションのあり方に合わせたルール作りが必要となります。
その一番基本的な法律が,区分所有法です。一般的な民事関係の基本法は民法ですが,そのルールの一部を分譲マンションに合わせて修正したものが区分所有法です。したがって,区分所有法は民法の特別法という言い方もされます。
次いで,マンション管理適正化法という法律があります。この法律は、マンションにおける良好な住環境の確保等を目的としたもので、マンション管理士の資格や義務などについて定め、また、マンションの管理業者についても規定しています。
近時は建築から一定の年数が経過したマンションが増えていることから、マンションの建替えの促進を図る目的で、マンション建替え円滑化法という法律も制定されています。
最後に、法律ではありませんが、国土交通省が作成していて、皆様にもなじみがあるものとして、標準管理規約が挙げられます。標準管理規約は、いわば各マンションの管理規約のひな形であり、多くのマンションが概ね標準管理規約を参考にして規約を作成されているものと思います。
このように、マンションに関係する法律等は多数存在しますので、管理組合、理事会の皆様は、よくご覧いただき、マンションの管理に活用していただくことが大切と考えます。
もし、理解の難しいところがありましたら、ご遠慮なく弁護士桑田までお問い合わせください。
投稿者 | 記事URL
2020年6月15日 月曜日
雑誌relife+で連載が始まりました!
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今日は皆様にお知らせです。
扶桑社さんから出版されているマンションのリノベーション雑誌「relife+(リライフプラス)」の中でマンショントラブルのケーススタディを担当することになりました。
「あるある!マンショントラブルのケーススタディ」というタイトルで、これまでの私の経験や裁判例をもとに、皆様のマンション内のよくあるトラブルにアドバイスをするという内容です。
これまでも雑誌や管理会社さんの機関紙での記事の掲載の経験はありましたが、一般に販売される雑誌での定期的な記事の担当は初体験ですので、今後も皆様のお役に立てるような情報や経験談を掲載していきたいと思っています。
ぜひ、一度、ご覧になってください。
投稿者 | 記事URL
2020年6月2日 火曜日
新型コロナウイルスの発生は「不可抗力」に当たるか
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、新型コロナウイルスの発生が取引に与える影響についてです。
ちなみに、私はマンショントラブルを手掛けていますが、他の法律問題も扱っていますし、企業の顧問もしています。
経営者からの相談は多数ありますし、交通事故や離婚や相続といった家族関係の問題もほぼ常時扱っています。
ときどき、マンション問題以外はしていないと思われる方もおりますので、念のためお知らせいたします。
話がそれてしまいましたので、戻ります。
契約書の中に「洪水、地震・・・その他不可抗力による債務の履行遅滞又は不能は、その責任を負わない」といった規定が書かれていることがありますが、これが不可抗力条項と呼ばれる条項です。
ですので、不可抗力に該当する場合は、契約上では自分が行うべき債務を行わなくても責任を負わなくてよいことになります。
そして、このブログを読まれている方の中には「新型ウイルスが発生したら、それは不可抗力になるのではないか」と思われる方も多いと思います。
もちろん、新型コロナウイルスが「不可抗力」に該当する可能性はあります。
ですが、直ちに新型コロナウイルス=不可抗力ではなく、ケースバイケースの検討が必要です。
例えば、その契約の内容、契約の期間、履行する場所などによっても不可抗力に当たるかどうかは違いがでるでしょう。
ライブハウスや飲食店など休業要請されている業種とそれ以外の業種によっても、当然違いが生じますので、
「不可抗力に該当するかどうか」は慎重に検討することが必要になります。
もっとも、実際の取引では不可抗力に当たるかどうかは、多岐の検討が必要です。
ブログを読まれている方の中には、自分の行うべき債務が不可抗力で履行できないものかどうか、判断がつかない方も多いと思いますので、判断に迷われたら、私にお気軽にご相談ください。直接、丁寧に対応いたします。
投稿者 | 記事URL
2020年6月1日 月曜日
クレーマー住民の傾向と対策(総会当日篇)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、クレーマー住民が出席する総会の当日の対応です。
前回説明しましたように、総会は事前準備が大切です。
もっとも、予期せぬ総会の妨害にあうこともありますが、これも総会運営の基本を押さえることで乗り切ることができます。
まず、議長には、議事進行権限がありますので、誰にいつどのような順番で発言させるかは、ある程度議長に裁量が認められています。
したがって、あまりに長時間の意見や同じ内容を繰り返す質問は打ち切ることができます。
議案に関係のない質問にも答える必要はありません。
なお、クレーマーだから一切発言させないとか、回答を拒否するということではありません。
議案の中心となる事項について説明することは当然のことです。
もっとも、そもそもどのタイミングで打ち切るべきか、議案と関係のある質問と言えるのか、といったことは一般の方では確認することが難しい事項ですので、総会の運営に悩まれた場合には当職までお気軽にご相談ください。
投稿者 | 記事URL
2020年6月1日 月曜日
クレーマー住民の傾向と対策(総会準備篇)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、マンションのクレーマー住民の出席する総会の準備です。
クレーマー住民は、総会で長時間の演説や、議題と関係のない事項に対する質問を行います。
このような場合に備えて、どのような総会の準備をすればよいでしょうか。
まず、たいていの管理会社では総会のシナリオを用意していると思います。
ただし、これは定型的なもので、必ずしもそのマンションに合っているわけではありません。
そこで、総会シナリオを個々のマンションの事情に合わせた最適化がとても重要であり、ここに弁護士の存在意義があります。
例えば、これまでのクレームから、クレーマーの興味関心のある議案が分かっていれば、慎重な説明をする必要があります。
また、想定問答集を用意しておくことも必要になります。
シナリオは基本的な説明事項ですが、その後の質疑応答でクレーマーがどのような質問をしてくるか想定し、回答も用意しておくことで、実際に質問されたときの戸惑いが軽くなります。その意味では、特に議長はリハーサルをしておくことも大切でしょう。
このように総会の事前準備は必要ですが、一般の方では、どのようなシナリオを作成したり、質問を予測して回答を考えることはとても大変なことですので、お困りの場合は弁護士桑田までお気軽にご相談ください。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (6)
- 2023年7月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2022年6月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (3)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (3)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (6)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (2)
- 2015年12月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年1月 (2)
- 2014年6月 (2)
- 2014年3月 (3)
- 2014年1月 (2)
- 2013年7月 (1)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (2)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (2)
- 2012年7月 (13)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (3)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (2)