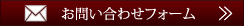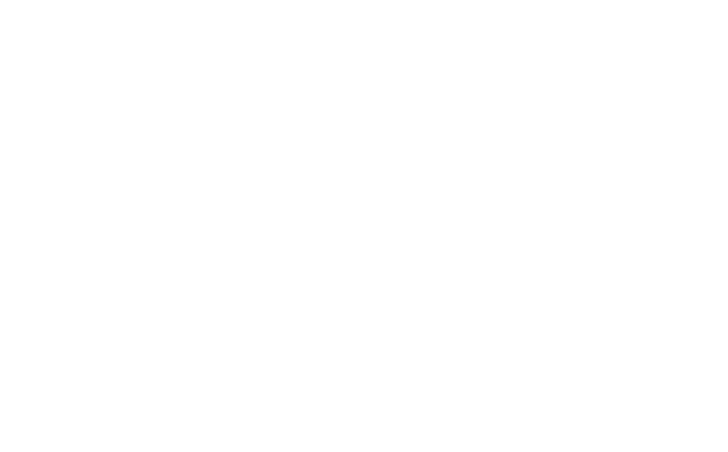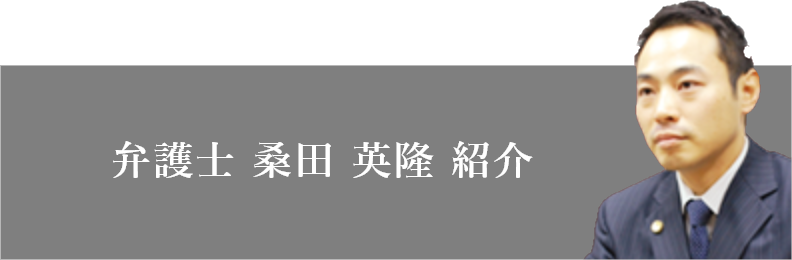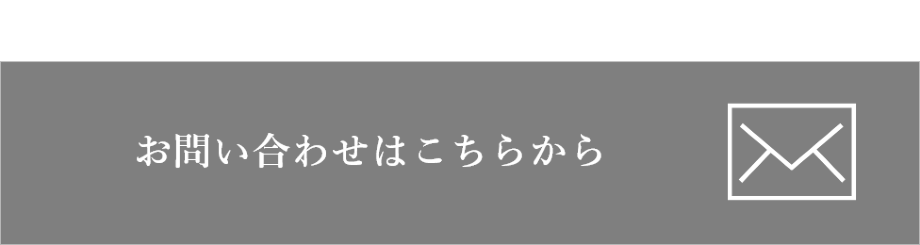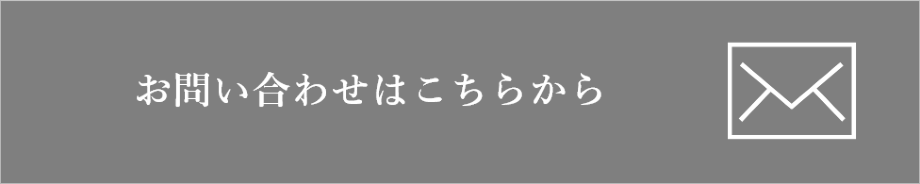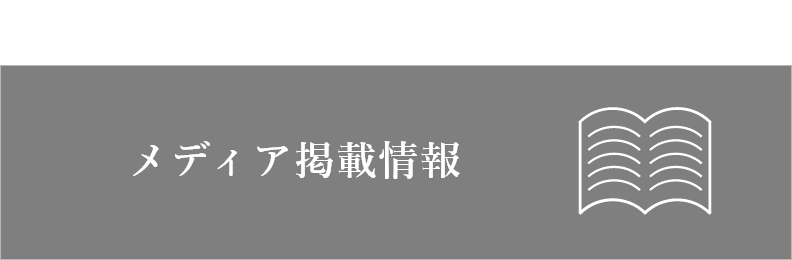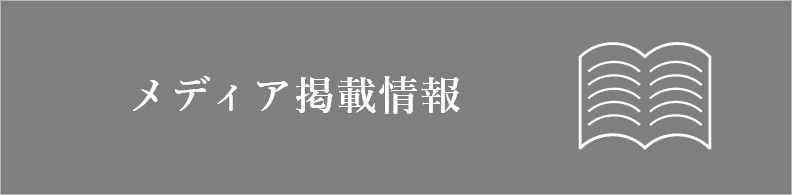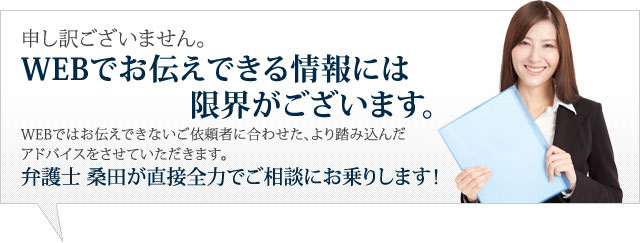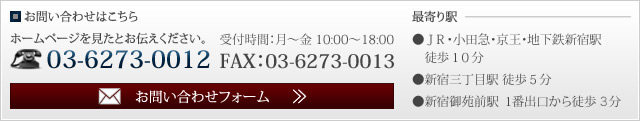弁護士桑田の活動日誌
2013年3月22日 金曜日
管理組合の会計帳簿等を閲覧謄写できるか
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは「組合員が管理組合の保管する会計帳簿等を閲覧謄写できるか」です。
組合員からこのような請求がされる例はときどき見受けられます。
その背後には理事会と当該組合員との感情的対立があることや,理事会の会計処理についての疑心暗鬼があるケースも決して少なくありません。では,閲覧や謄写は認められるのでしょうか。
裁判例などを見ると,原則として団体の規約によって自主的に決めるべきと考えているようです。また,標準管理規約64条は,会計帳簿等について「理由を付した書面による請求があったときは,これらを閲覧させなければならない」とあるので,標準管理規約をもとに規約が作成されていれば,会計帳簿等の閲覧が出来る場合が多いでしょう。
それでは,規約上,閲覧についてだけ条項が設けられている場合に謄写の請求も出来るのでしょうか。
裁判例はまだ結論が分かれており,確たる方向性が出ているわけではありません。
謄写を認める裁判例は,会計帳簿等の数字の対比・検討には閲覧だけでは足りず謄写を求めることが出来ると考えています。
一方,謄写を否定する裁判例は,閲覧請求を認めつつ謄写請求について何らの規定もないことや謄写の費用負担が発生することなどを理由に謄写できないとしています。
いずれも不合理というわけではありませんから,かりに謄写請求を認める裁判を起こす場合でも敗訴リスクがあることも前提にしなければいけないことにご注意下さい。
その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。
マンション住戸の目的外使用は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html
マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
マンション内の水漏れ事故については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html
マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/
投稿者 | 記事URL
2013年3月12日 火曜日
マンション住宅部分の目的外利用の可否
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「管理規約で住居以外の使用が禁止されている場合の目的外使用について」です。
マンションの中には,管理規約で「本来の住居以外の目的に使用することを禁止する」との条項を設ける例がよくあります。
これは,店舗や事務所などで利用されると不特定多数の外部者が出入りし良好な住環境や安全を確保できないと考えるからです。
ところが,実際には,住戸を会社の事務所や店舗などに利用する事例が見受けられます。そのため,管理組合が管理規約違反として区分所有法57条により使用禁止請求を行います。この請求が認められるかは「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかがポイントになります。この点については後記のように複数の裁判例が出ていますが,単に目的外使用をして管理規約に反するだけでなく,行為の性質や程度からみて受忍限度を超えるかを総合的に判断する裁判例が多いようです。
この点の裁判例は以下のようなものがあります。病院の看護師等の幼児のための保育室として使用することが許されないとした事例(横浜地裁平成6年9月9日),カイロプラクティック治療院として使用することが「区分所有者全員の共同の利益」に反するとしつつ管理組合の請求は権利濫用として否定した事例(東京地裁平成17年6月23日),無認可託児所として使用することが許されないとした事例(東京地裁平成18年3月30日),税理士事務所として使用することが許されないとした事例(東京高裁平成23年11月24日)などです。
これらの裁判例から見る目的外使用の禁止の可否の判断要素はおおよそ以下の通りと考えられます。
①目的外使用による被害の程度(騒音の有無や程度,近隣住戸からの苦情の有無,不特定多数の外部者の利用の有無)
②従前の管理組合の態度(他の目的外使用者にも使用禁止を徹底していたか等)
このように,①目的外使用の程度が甚だしく受忍限度を超えていれば目的外使用の禁止が認められる方向になります。
一方,仮に目的外使用をしていたとしても,他にも店舗利用や事務所として利用している区分所有者が多数いる中で②管理組合が特に規約違反を主張していないのに,一部の区分所有者だけ使用禁止を求める場合は権利濫用として否定される場合もあります。
もっとも,目的外使用の程度の判断などはなかなか難しいと思いますので,お気軽にご相談下さい。
その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。
マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
マンション内の水漏れ事故については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html
マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/
投稿者 | 記事URL
2013年1月31日 木曜日
慰謝料1日4200円,休業損害1日5700円とは?
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,交通事故の傷害慰謝料と休業損害の計算方法です。
交通事故に遭遇すると,加害者側保険会社から通院期間中の傷害慰謝料と休業損害の提案を受けることがあります。
その際,「傷害慰謝料 1日当たり4200円×実通院日数×2倍」とか「休業損害 1日5700円×実通院日数」という提案を受けることが多いと思います。なぜ,このような基準が提示されるのでしょうか。
実は,これは自賠責保険の基準です。
傷害慰謝料は,1日4200円に治療期間または実通院日数の2倍をかけて,どちらか少ない方の金額を慰謝料とします。
通院の場合,二日に一度以上診察を受けることは少ないでしょうから,4200円に実通院日数の2倍を掛けた金額となるのです。
また,休業損害も自賠責保険では原則1日5700円とし,明らかにそれを超える場合には1日1万9000円を限度に実額が認められます。
では,任意保険会社が自賠責保険の基準を提案するのはどうしてでしょうか。
それは,保険金の支払いの仕組みに原因があります。
もともと任意保険は,自賠責保険の支払だけではてん補されない損害について支払われるのが原則です。
ですが,実際には被害者が二度請求する手間を省くため,任意保険会社が自賠責保険分も含めた損害全額を支払い,自賠責保険分は,後に自賠責保険会社に求償するわけです。そこで,任意保険会社が,自賠責保険の基準で被害者と合意してしまえば,全額自賠責保険会社に求償でき,任意保険会社は全く負担しなくて良いことになります。
もっとも,被害者が,その提案に応じる義務があるわけではありません。
日本弁護士連合会交通事故相談センター(私も所属しています)東京支部の作成した「損害賠償額算定基準」にはより高額の慰謝料基準が記載されています。休業損害も,1日5700円に限定されず実額を基準に請求すべきです。
とはいえ,交通事故の専門家である保険会社との交渉は苦労が多いと思います。
私にご相談いただければ,丁寧に説明致します。
その他,交通事故のご相談は以下をご覧下さい。
示談あっせんする機関については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-32-342968.html
交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-30-320861.html
後遺障害の等級認定については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-24-309253.html
弁護士特約の利用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-19-301786.html
交通事故と時効の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-14-294651.html
その他の交通事故全般のご相談については
http://www.kuwata-lawoffice.net/jiko/
投稿者 | 記事URL
2013年1月23日 水曜日
相続税増税の東京への影響と対策
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「相続税の改正に対する東京への影響と対策」です。
本日の日経新聞によると,2013年税制改正について,自公民の3党間で相続税の増税で合意したとのことです。
主要3党の合意ですから,実現する可能性がかなり高いものと思われます。
その内容は,最高税率の引き上げと基礎控除の縮小です。
相続財産6億円超の部分に55%の税率を新たに設定し,2億円超3億円までの部分の税率も40%から45%に引き上げました。
また,相続税には,課税対象とされない部分(基礎控除)があります。これまで,5000万円+1000万円×法定相続人数が基礎控除とされていました。つまり,法定相続人が一人だとしても,6000万円までは相続税がかからなかったのです。ところが,今回の改正では,基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人数」となりました。そのため,いわゆる富裕層だけでなく,たとえば不動産価格が4000万円である程度の預貯金などを持つ方も相続税の対象となります。特に東京は地価が高いため,東京に不動産を持つ方が相続税の対象となる可能性は高まり,10%超となるとの試算もあります。
このように,これまでは相続税と無縁と思われた方でも,相続税対策をする必要が出てきました。
まず税務的な対策としては,配偶者控除の利用や相続時精算課税制度を利用した節税が考えられます。
加えて「遺産を誰にどのように相続させるのが節税や相続人間のトラブルを防げるか」を検討して遺言を作ることをお勧めします。
私は,税理士法人とも提携しています。法的,税務的にもっとも適切な相続税対策を行うことができますので,お気軽にご相談下さい。
その他のご相談については,相続全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/souzoku/#a02
未成年者の関係する遺産分割については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-33-343015.html
遺言執行者については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-27-314543.html
遺言の作成については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-13-285125.html
相続の準備については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-36-347542.html
投稿者 | 記事URL
2013年1月23日 水曜日
八日目の蝉
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回は,いつものような法律テーマではなく,最近,見た映画の雑感です。
気楽にお聞き流し下さい。
「八日目の蝉」は,角田光代原作,平成23年4月公開の映画です。
当時から気になっていましたが,私はテレビ放送を録画したものを,さらにだいぶ遅れて見たわけです(^_^;)
女性が不倫相手の子供(新生児)を誘拐し,自分の子供として育てるというストーリ-でした。
子供が誘拐犯を自分の母親と思って育つことによる悲劇,誘拐された後の真の両親との関係などが描かれています。
私はそれほど映画を見る方ではありませんし感動しやすい質でもありませんが,この映画には泣かされました。
私にも2歳になる長男がいるからかも知れません。
「もし子供が誘拐されていたら」とか,勝手に想像してしまいます。逆に,誘拐犯の立場でも,0歳から4歳まで我が子として育てており,引き離されることには「もし,自分の子供と無理矢理別れされたら」と,やはり想像をしてしまうのです。
この映画を見ると,小説家や脚本家が,いかに想像力を駆け巡らせているか,いかに人をよく観察しているか,が分かります。
人の気持ちが分からないと,感動させることは出来ないでしょうし,セリフ一つとっても「あるある,子供の言いそうなこと」という言い回しが多く驚きました。
実は,弁護士という職業も「想像力をめぐらし,人を観察する」ことがとても大切です。たとえば,相手方はから「1000万円を貸したから返せ」と返還を求められている場合でも「そのような大金であれば,預金など出所がはっきりしているはずであるし,振込送金手続をしていないとおかしい」「通帳のような証拠が出てこないのは,本当は貸していないからだ」として反論するのです。
ですから,小説家や脚本家の仕事には尊敬の念がありますし,見習おうと決意も新たにします。
以上,とりとめのない雑感でしたm(_ _)m
投稿者 | 記事URL
2013年1月17日 木曜日
中小企業金融円滑化法の終了と破産(倒産)
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,特に中小企業の方の興味のある中小企業金融円滑化法(金融円滑化法)の行方です。
金融円滑化法は,中小企業の資金繰り支援のため,平成21年12月から施行されています。
その内容は,中小企業等の債務者から申込みがあった場合,金融機関は返済期限の延長等の負担軽減を行う努力義務を負うというものです。返済期限を延長できた中小企業は約40万社とされています。
ところが,金融円滑化法は,今年の3月末をもって終了します。与党の一部から再延長を求める意見もあるようですが,終了はどうやら既定路線のようです。マスコミによると,金融円滑化法終了により40万社のうち,かなりの会社の資金繰りが窮すると予定されています。
このような場合の対策は,大別して「事業再生」と「破産」が考えられます。
どの会社も,好んで破産したいわけはありません。ですから,弁護士も極力事業再生が出来ないかを検討します。
営業キャッシュフローが回るか,本業の立て直しが出来るか,そしてなにより経営者に「私財を投じても立て直す」という気概があるか,を見ながら,事業再生できるかを慎重に判断することになります。
もし,金融円滑化法の終了による資金繰りに不安がある場合には,お早めにご相談下さい。
その他,会社関係のテーマは以下の通りです。
,中小企業法務全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/
中小企業の顧問弁護士の活動については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-9-277620.html
定年後の継続雇用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-26-310698.html
企業による復職支援については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-16-298446.html
債権回収の相談事例については
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/#__question1_1__
投稿者 | 記事URL
2012年12月17日 月曜日
欠陥住宅問題と住宅紛争審査会
こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,欠陥住宅トラブルの解決のために「住宅紛争審査会」を利用する場合のメリットについてです。
実は,私も平成24年9月から,東京弁護士会の住宅紛争審査会の紛争処理委員を拝命しました。
住宅紛争審査会は住宅品確法によって設置された紛争処理機関ですが,分譲マンションも対象となっています。
ですから,マンション管理士の資格をもつ私も問題解決の一助になれるのではないか,と考えた次第です。
住宅紛争審査会の扱う住宅は,住宅品確法に基づき建設住宅性能評価書が交付された評価住宅や住宅瑕疵担保履行法に基づき住宅化し担保責任保険が付された保険付き住宅に限られますが,以下のように訴訟にはないメリットがあります。
まず,弁護士と建築士という住宅紛争の専門家による公平な判断を得られること,審理期日5回が目途で早期の解決が図れること,申請手数料が1万円と安価であることなどです。
また,住宅紛争審査会の利用の前に,まず相談したいというニーズに応えるため,現在,各弁護士会では住宅専門相談の体制を整えています。弁護士と建築士が同席するという方法をとっており,相談者からも高い評価を得ているようです。東京での相談状況も現在増加傾向を示しているとのことです。
欠陥マンションも含めて欠陥住宅問題がクローズアップされています。もし,お困りの場合には住宅紛争審査会を利用することも検討する価値があると思います。
投稿者 | 記事URL
2012年11月12日 月曜日
東京都立病院による未払医療費の債権回収
こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,都立病院の行った未払いの医療費の回収についてです。
先日の日経新聞の記事に掲載されていたものです。
記事は,東京都立8病院が未払いの医療費の回収に成功したことを伝えています。
その方法は,「治療費の回収を専門に手掛ける非常勤職員の配置」と「回収業務の委任契約を弁護士と締結」することです。
まず,専門職員が毎日多いときは20人程度に電話したり月に1,2回直接訪問して支払を促します。
また,院長の代理として弁護士が支払を求める文書を作成し,代理人として文書には弁護士名も記載するようです。
支払い能力があるにもかかわらず無視する悪質な未払者に対しては裁判所を利用した支払督促を行うとのことでした。
都庁の都病院経営本部によると「ここまで強い措置を取れば大半の人が支払に応じる」とのことです。一方,生活の困窮で支払が困難な方には弁護士が公的補助制度を活用した返済を助言しているようです。
最近では,病院に限らず地方自治体でも弁護士を活用して債権回収を図る例が増えているようです。
現在の経済状況では治療費の他マンションの管理費などの未払も増加しており,弁護士を活用した債権回収が重要な手段となっており,また一考の価値があると思います。
その他,債権回収の相談事例については
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/#__question1_1__
支払督促については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-39-350957.html
をご覧下さい。
投稿者 | 記事URL
2012年10月2日 火曜日
賃料を滞納するテナントを退去させる方法
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,ビルテナントなどが賃料を支払わない場合に,どのようにして退去を求めるか,ということです。
経済事情が悪化をたどる昨今,入居者が賃料を何ヶ月も滞納することが大変増えています。
ですから,ビルや投資用マンションのオーナーさんにとって興味関心の強い事柄でしょう。
賃料を滞納した入居者の中には,「後もう少し待ってくれれば,お金が入るので,かならずまとめて払う」と支払い猶予を求める方がいます。そのような場合には具体的に「いつ,どのような理由で,いくら入金されるのか」を確認することが必要でしょう。私の経験からすると,数ヶ月賃料を払えない入居者に急に一定の金額の入金があるというのは極めて稀で,容易に信用することはできません。そこで,よほど信頼できる入金の事情がない限り,賃料未払を理由とする契約解除と退去の方法を検討することになります。
退去させる一番良い方法は,実は話し合いによる賃貸借契約の合意解約と任意の退去です。建物明渡請求訴訟等の法的手段よりも早期に解決できますし,退去自体も強制的ではなくスムーズに進めることができます。そのためには,たとえば退去まで一定期間の猶予を与えるとか,賃料の一部を免除することも考えて良いでしょう。早期に退去してもらい,新しい入居者から毎月確実に入金を受ける方が,オーナーのメリットは大きいです。
一方,賃借人が全く連絡がつかない(連絡しても出てくれない)とか,反抗的な態度が鮮明であるような場合には,いたずらに時間を掛けず,建物明渡請求訴訟を提起することが必要です。ただし,2ヶ月程度の賃料の延滞では契約解除が認められない可能性がありますので,ご注意下さい。
建物明渡請求訴訟をする際には,仮執行宣言も忘れずに求めて下さい。仮執行宣言は,判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる制度なので,たとえば第1審で勝訴して仮執行宣言が付けられた場合,賃借人が時間稼ぎのために控訴をしてきても,明渡の強制執行が可能になります。「仮の強制執行」といっても,実際に建物退去を強制されます。これを回避するには賃借人側は強制執行停止決定の申立をすることになりますが,その前提として賃料の1年分前後の担保金を積むことが求められます(事情によって担保金額には幅があります)。何ヶ月も賃料を滞納していた賃借人が1年の賃料に相当する担保金を積むことはほとんど不可能ですから,仮執行宣言による建物明渡は,オーナー側からすると大変強力な武器になるわけです。
このように,種々の手段がありますが,どのような手段で退去を求めるのが適当か判断がつきにくいこともあると思います。そのような場合には,お気軽にご相談下さい。
投稿者 | 記事URL
2012年9月21日 金曜日
老人ホームの入居一時金の返還
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「老人ホームの入居時に多額の一時金を支払った場合,退去あるいは死亡時に返してもらえるか」です。
老人ホームの入居一時金(入居申込金,入居保証金などの名称の場合もあります)は,一般に数百万円から数千万円と大変高額な場合が多い反面,高齢者ゆえに入居後短期間で死亡したり,病院への入院のため退去せざるを得ない場合が多々見られます。
そのような場合には,入居金を返してもらいたいと考えることも当然ですが,実際に返還請求することは可能なのでしょうか。
入居一時金については,多くの老人ホームの入居契約では,まず初期償却(2~3割程度が多いようです),その後,一定の期間(5年とか7年など)で償却する制度を設けているのが一般的です。ところが,中にはごく短期間で退去した場合でも全く返金されないケースなども見受けられてトラブルが発生したため,平成18年の厚生労働省の指導指針で90日間以内の解約については利用料や現状回復費用等を除いた全額が返還されるルールが設けられました。さらに,老人福祉法の改正により,平成24年4月以降の入居については老人福祉法規則に従った前払い金の返還が法定され,法的な効力が付与されました。
なお,平成24年4月以前に入居された方の場合で,90日ルールなども入居契約書に記載されていない場合でも,入居金が返還される可能性はあります。契約の解除に伴い消費者が不当な金銭的負担を強いられないことを目的とする消費者契約法第9条や,消費者の利益を一方的に害する条項を無効とすることを定めた消費者契約法第10条の違反に該当する場合もあり得るからです。
これらの条項に該当するかどうかは,法的判断を必要とします。また,高齢の入居者の中には,老人ホームとの返還交渉をご自身で行うことに心理的負担や不安を覚えられる方もおられると思います。そのような場合にはお気軽にご連絡下さい。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (6)
- 2023年7月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2022年6月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (3)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (3)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (6)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (2)
- 2015年12月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年1月 (2)
- 2014年6月 (2)
- 2014年3月 (3)
- 2014年1月 (2)
- 2013年7月 (1)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (2)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (2)
- 2012年7月 (13)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (3)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (2)