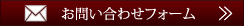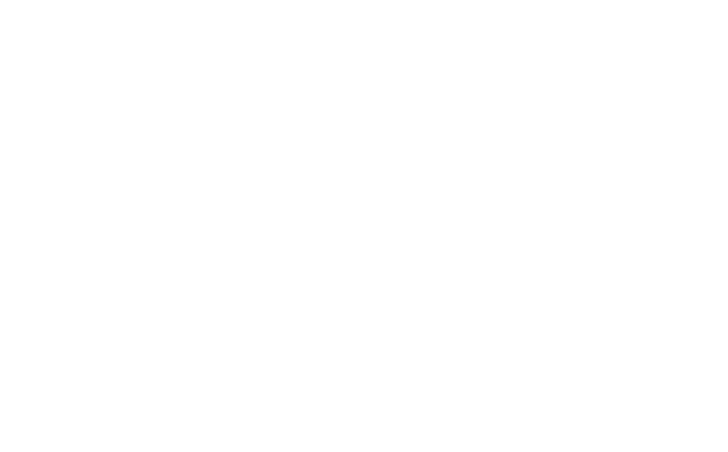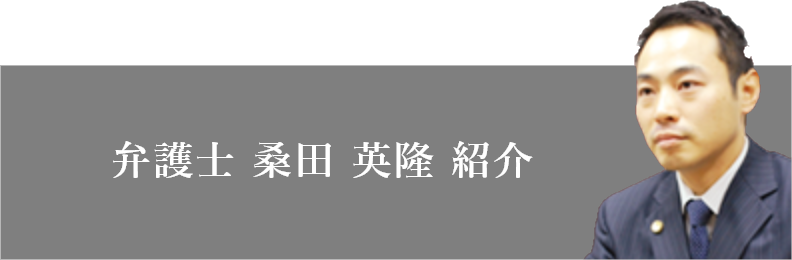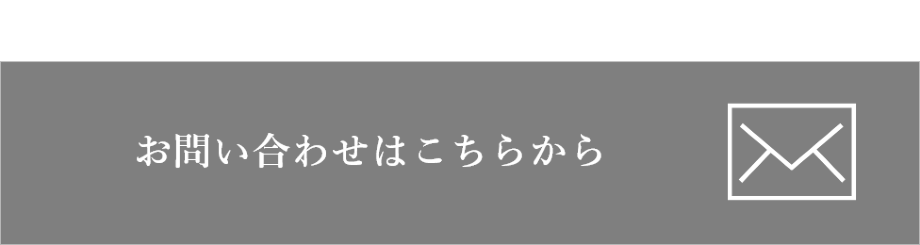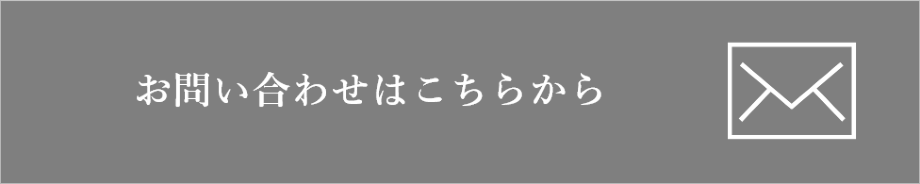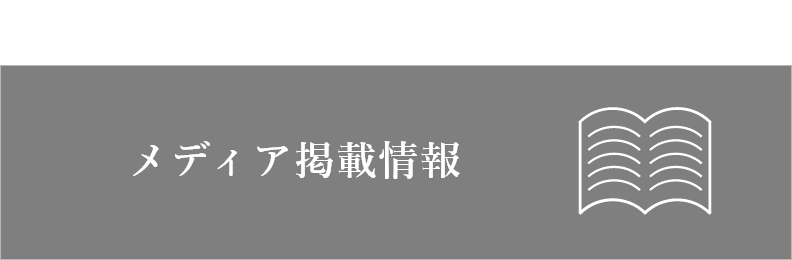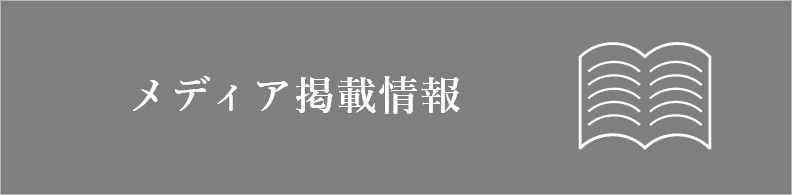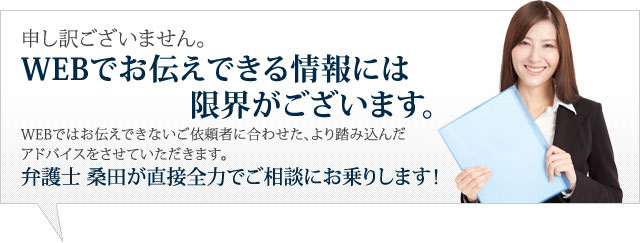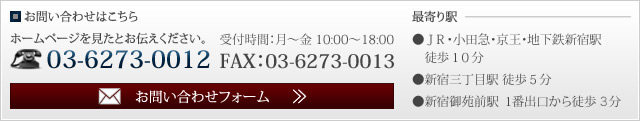弁護士桑田の活動日誌
2018年2月22日 木曜日
理事長の解任を認める最高裁と管理規約への影響
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,理事による理事長の解任を認めた最高裁平成29年12月18日判決のご紹介です。
新聞等でも大きく取り扱われたので,ご存じの方も多いと思います。
この事件は,理事の過半数の賛成で理事長を解任して,単なる理事とすることができるかどうかが争われました。
私の感覚としては,そもそも理事長は,理事が互選する規約がある場合,選任する権限がある者が解任する権限があるのは当然と思っていましたので,
このような争いが最高裁に持ち込まれたことも驚きでした。
ですが,原審である福岡高裁は,「規約には選任の定めはあるが,これは解任についての定めではない」「役員の解任は総会の議決事項とされている」との理由で,理事の過半数で理事長を解任することは許されないと判断していました。
一方,最高裁は,理事の互選で理事長を選任できる定めがあることについて「このような定めは,理事の過半数の一致により理事長の職を解き,別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが,区分所有者の合理的意思に合致する」として,理事の過半数の一致により理事長を解任することができるとしました。
最高裁の結論はとても常識的で,納得がいくものです。もっとも,福岡高裁のような判断がなされたことも事実です。
ですから,標準管理規約の記載だけでも理事による理事長の解任は認められるでしょうが,より慎重を期して「理事の互選により選任し,又はその過半数により解任することができる」などと規定することも有用と考えます。
現在,管理規約の改正をご検討の理事会の皆様にはこの点にもご留意下さい。
投稿者 | 記事URL
2018年2月9日 金曜日
マンションの顧問弁護士活用法その2
こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションの顧問弁護士活用法の第2回です。
前回は顧問弁護士がどのようなときに役に立つのかについて記載しましたが,
今回は顧問弁護士が具体的にどのように管理組合と関わっているのかについてご説明します。
まず,管理組合の運営は理事会を通じて行い,日常の業務は管理会社がアドバイスをしていますので,理事長や管理会社から法律上の相談を受けることが多いです。
例えば,駐輪場に放置された自転車の扱いとかマンションの住民同士のトラブルへの対応などです。
後でお話ししますが,クレーマーのような住民からの理不尽な要求への対応を相談される例も多数あります。
また,管理規約や使用細則などの作成や確認の依頼を受けることもよくあることです。最近ではシェアハウスや民泊を禁止する規約の改正や暴力団排除条項などの新設の相談があります。
これらは,ひな形もありますが,個々のマンションによって事情が異なりますので,その事情にマッチさせつつ法律の要請に適うようにすることが必要になります。
管理組合総会の準備や総会当日の立ち会いなども顧問弁護士の重要な仕事になります。
顧問弁護士を依頼しようとするマンションというのは,住民の一部にクレーマーあるいはトラブルメーカーという人物がいるケースも多く,総会でも高圧的な発言をしてくることがあります。
そのような場合に備えて,想定問答集の作成や不規則発言の止め方の指導なども行います。
その他,クレーマーなどに揚げ足を取られないよう総会議事録,理事会議事録の記載をチェックする作業もあります。
このように顧問弁護士の仕事は非常に多岐にわたるのです。
ところで,もう一つ気になるのが,弁護士の顧問料が高額ではないか,という疑問です。
私のホームページをご覧頂きますと,月額5万円(税抜き)から始まり,単棟型か住宅店舗複合用途型か団地かという種類や戸数によって顧問料が決まりますので,おそらく他のマンション管理士の方と比して高額ということはないと思います。
また,大規模な団地でも最初から高額の顧問料を支払うことに抵抗感があるのは当然です。例えば当面月額5万円(税抜き)とする例もありますので,お気軽にご相談下さい。
投稿者 | 記事URL
2018年2月9日 金曜日
マンションの顧問弁護士活用法その1
こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションにおいて顧問弁護士をどのように活用するかということです。
顧問弁護士は実際に依頼されれば有効性はかなり実感してもらえると思いますが,実際の依頼例は少ないと思いますので,私の経験に照らして顧問弁護士の業務を説明します。
その前に,そもそも顧問弁護士が本当に必要か,という疑問があると思います。
かなり多くの疑問として,管理会社と委託契約を結んでおり,疑問があれば管理会社に聞けばよいという意見があります。
また,裁判などでどうしても必要なときだけスポット的に依頼すれば良いという意見もあります。
管理会社の担当者は,それなりに研鑽を積んでいれば,通常の業務であれば,確かに足りるかも知れません。
ですが,管理規約や細則の変更は法律技術的な側面が強く,区分所有法の知識が必要であったり,そのマンションの実情に応じた条文の作り込みが必要です。
そのような場合には,日常的に契約書や規則類を確認・作成している弁護士でないと対応しきれないときがあります。
また,裁判が起きないように予防的な法務を行ったり,裁判になったときに不利にならないよう事前に証拠化しておく方が,じつはスポットで高額の弁護士費用を支払うより安上がりなケースは多数あります。
裁判になるほどではないが,どう対応すれば違法にならないか,ということを迷うケースでも,いつでも相談できる弁護士がいることはとても便利に感じていただけると思います。
少し長くなりましたので,実際の顧問弁護士の仕事内容については,別の記事でご紹介します。
私は顧問契約にも対応していますので,お気軽にご相談下さい。
投稿者 | 記事URL
2018年2月9日 金曜日
マンション内でのゴミ屋敷トラブル
こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションの住戸がゴミ屋敷となった場合の解決策です。
最近は戸建てだけでなくマンションでもゴミ屋敷が問題となることが増えてきているようです。
では,このトラブルにどのように対応するのが良いのでしょうか。
まず,管理組合が率先して共用部分を清潔に保ち,マンション全体でゴミ屋敷を作りにくい雰囲気を形成することが考えられます。
また,汚れや臭気が目立つ住戸が出たときには,素早く掲示板で,住戸を特定しないように配慮しながら注意喚起する方法もあります。
それでも改善されないときは,理事長名や管理会社名で,直接,注意文書を交付して改善を促す手段もあるでしょう。
ただし,自分の住戸をゴミ屋敷にしてしまう人物ですと,このような方策を採っても,効果がないことも十分考えられます。
この記事をご覧の皆様(理事長,理事,管理会社,近隣にお住まいの住戸の方)も,万策尽きて,困り果てて,この記事を読まれているのではないでしょうか。
このような場合には,やはり法的対応つまり裁判を起こすしかないということになります。
具体的には,区分所有法第57条による利益背反行為の停止請求,第58条による専有部分の使用禁止請求,第59条による区分所有権の競売請求です。
ただし,それぞれの要件や効果が異なるので,どの条項を利用して訴訟をするかは慎重な検討が必要です。
例えば,利益背反行為の停止請求で勝訴しても,言うことを聞いてくれなければ,さらなる手段が必要になります。
その他に,損害賠償請求で勝訴した上で,損害金の回収のために住戸の不動産競売を申し立て,結果として,ゴミ屋敷の所有者を追い出す方法もあります。
損害の内容としては,例えば,共用部分の清掃費用や裁判の準備のための臭気測定費用,弁護士費用などが考えられるでしょう。
いずれにせよ,実際に溜まったゴミをどのように処理するのかなど,実務上の問題もありますので,
もしマンション内のゴミ屋敷のトラブルでお困りでしたら,私までお気軽にご相談下さい。
投稿者 | 記事URL
2017年11月28日 火曜日
マンショントラブルにおける弁護士費用負担の裁判例
皆さんこんにちは,弁護士の桑田です。
先日,マンショントラブルが発生し,管理組合が区分所有者を相手に裁判を起こした場合の弁護士費用についてご紹介しました。
標準管理規約では,弁護士費用をトラブルメーカーである区分所有者に請求できる場合があることを規定しています。
それでは,具体的には裁判例では管理組合の弁護士費用について,どのように扱われているのでしょうか。
近年の裁判例を確認してみたところ,管理規約上に弁護士費用の負担が規定してある場合には,全額支払われる例が多いようです。
東京高等裁判所平成26年4月16日判決は,弁護士費用を違約として請求できる規定について「このような定めは合理的なものであり,違約金の性格は違約罰(制裁金)と解するのが相当である。したがって,違約金としての弁護士費用は,管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解される」と判示し,管理組合の請求する弁護士費用全額を認めています。
一方,裁判例の中には「本件弁護士費用等条項は、違約金として必要な弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を請求できるとするのみであって、弁護士費用の算定方法を明らかにしていないから、相当な弁護士費用を請求できることを定めた規定と解するのが相当である」として,「不法行為と相当な因果関係を有する弁護士費用が損害額の10%とされていることを考慮すれば、本件においては、認容額の10%相当額について、相当な弁護士費用であると認める」として,認容額の10%に限った裁判例もあります。あるいは,認定事実と弁論の全趣旨から一定金額が相当と裁判所が金額を決めた例もあります。
以上からすると,実際に管理組合が支払った金額を前提としつつ,認定した事実や難易度を考慮して,請求額が高額である場合には金額を調整する側面があるのかも知れません。
いずれにせよ,管理組合としては,弁護士費用を持ち出しにせずに対応できることから,この規定を定めて十分に活用することが求められます。
投稿者 | 記事URL
2017年11月1日 水曜日
マンション裁判における弁護士費用の負担
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンション裁判における弁護士費用の負担です。
具体的には「トラブルを起こした区分所有者に対して,管理組合が裁判を起こした場合,その区分所有者に弁護士費用を請求できるか」という問題です。
まず,原則として,不法行為を除いて,弁護士費用は,それぞれの当事者が自分の依頼した弁護士の費用を負担することになります。
不法行為でも請求額の1割を弁護士費用とするのが概ね慣例ですから,通常は弁護士費用全額を請求できません。
ただし,マンションにおける裁判は別の考慮が働きます。
この点については,標準管理規約に記載があります。
標準管理規約は,第67条第3項で,区分所有者が規約や細則等に違反したとき,敷地又は共用部分等で不法行為を行ったときに管理組合が採れる手段の一つとして裁判を起こすことも規定しています。
その上で,次の第4項で「前項の訴えを提起する場合,理事長は,請求の相手方に対し,違約金としての弁護士費用及び差止めの諸費用を請求することができる」とあります。
そのため,マンションの裁判では管理組合の弁護士費用を相手方区分所有者に請求できる場合があるのです。
具体的に,どのような場合にいくらが認められるのかについてはいくつか裁判例がありますが,長くなりましたので,次回にお話ししたいと思います。
管理組合の皆様の中にも,クレーマーあるいはトラブル区分所有者に対して訴訟を提起したいと思いながら,弁護士費用が負担で裁判に踏み切れない方もいると思います。
その場合は管理規約をご確認下さい。もし,標準管理規約とは違って,弁護士費用を請求できる規定がなかったとしても,規約を改正した上で裁判を起こすことも考えられます。
いろいろな方法がありますので,ぜひ弁護士桑田までご連絡下さい。
投稿者 | 記事URL
2017年10月31日 火曜日
マンションの漏水と個人賠償責任保険
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションで漏水事故が起きた場合の個人賠償責任保険の利用についてです。
マンションには廊下や外壁のような共用部分と区分所有者がそれぞれ所有する専有部分があります。
専有部分での水漏れが原因で下の階に被害を与えてしまったような場合にはどのような保険が使えるでしょうか。
通常,分譲マンションでは,管理組合が,共用部分のリスク管理として火災保険等の保険に加入しています。
そして,この保険の特約として,区分所有者が専有部分で漏水してしまったような場合に備えて,
個人賠償責任保険が付されている例が多いのです。
そのため,自分が漏水事故を起こした場合には,管理組合を通じて保険を利用することを是非考えて下さい。
詳しい保険の内容は,管理組合の加入している保険会社で確認することができます。
なお,個人賠償責任保険は漏水事故だけに使われるわけではありません。
居住者の方の子供の自転車事故なども対象になるケースがありますので,広く活用できるものです。
投稿者 | 記事URL
2017年10月25日 水曜日
マンション修繕積立金の管理
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今日のテーマは,マンション修繕積立金の管理についてです。
先日,NHKで「追跡,マンション修繕工事の闇」という番組が放送されていました。
内容は,区分所有者が積み立てた修繕積立金を,大規模修繕工事の際,設計コンサルタントが工事代金を水増しして,工事会社からバックマージンを得るという手法でした。
この点は,国土交通省も問題視し,平成29年1月の通知で,相談窓口の周知を行っていました。
番組の中では,コンサルタントが義務を果たしていなければ損害賠償や背任罪に該当することを指摘した上で,実際には,裏でバックマージンをもらったことの立証が困難であると説明していました。
この点はまさにそのとおりで,やはり裏で行われた行為を明らかにすることは相当難しいと思います。
番組では,対策としてマンション管理センターなどの相談窓口の紹介や,何よりもマンションの区分所有者が大規模修繕に関心を持つことの必要性を強調していました。
この指摘も最もなのですが,実際の問題として,大規模修繕に無関心の区分所有者が多く,関心を持たせることも大変な労力と思います。
私たちのような弁護士の努力も必要と感じましたし,技術的な側面はやはり一級建築士の力を借りることも多いと思います。
こうした問題にも積極的に取り組みたいと意を新たにしました。
投稿者 | 記事URL
2017年7月25日 火曜日
マンション民泊と管理規約
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは「マンションでの民泊について管理規約でどのように対応するか」です。
昨日,新聞各紙で,例えば「マンション民泊 可否を規約に」「国交省,管理組合に要請へ」といった記事が掲載されていました。このブログをお読みの方にも記事を目にされた方は多いと思います。
民泊には急増する訪日外国人の宿泊先となったり,区分所有者も宿泊料金を得られるという利点はあります。
一方,静かな環境で子育てをしたいというファミリータイプのマンションなどでは,見知らぬ人物が頻繁に出入りするとなると,不安を覚えることもあるでしょう。
そこで,国交省は,民泊の可否を標準管理規約に盛り込むことにしたようです。これは,平成29年6月に,民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法が成立したことの影響でもあります。
もともと,標準管理規約第12条には「区分所有者は,その専有部分を専ら住宅として使用するものとし,他の用途に供してはならない」と定められています。そこで,その次に第2項として,民泊を認める場合は「住宅宿泊事業に使用することができる」と,認めない場合は「住宅宿泊事業に使用してはならない」という条項を加える予定です。
そのため,管理組合としては,民泊を認めるにせよ認めないにせよ,自身のマンションの管理規約を変更することが求められていると言えます。
もっとも,管理規約の変更は技術的な側面もありますので,理事会だけで対応することには難しい側面があります。
もし,理事長や理事会の方がお困りの際には,弁護士桑田までお気軽にご相談下さい。
マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/
マンション住戸の目的外使用は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html
マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
マンション内の水漏れ事故については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html
マンション管理士については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/07/post-51-568373.html
マンション管理組合や理事会と管理会社の間のトラブルについては
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2014/03/post-55-779280.html
投稿者 | 記事URL
2017年3月22日 水曜日
マンション共用部分を賃貸に出す場合の問題点
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,管理組合がマンションの共用部分を第三者に賃貸する場合の問題点についてです。
この点については,携帯電話の基地局をマンションの屋上に設置するために賃貸することの是非が問われた裁判例があります。
原審である地方裁判所では,民法第602条を超える期間の賃貸借は処分行為であって,原則として区分所有者全員で行うべきと判示しました。
ところが,控訴審である高等裁判所では,区分所有法は民法の特別法であるから,区分所有建物の共用部分の賃貸借には民法第602条の適用は排除されるとしました。
その上で,特別決議が必要な場合か普通決議で足りる場合かを検討した上で,普通決議で足りると判示し,結論が分かれました。
また,共用部分の変更については,専有部分等の使用に特別の影響を受ける場合に専有部分を所有する組合員等の承諾が必要とされています。
そこで,組合員側が,特別の影響を受けるのに自分の承諾を得ていないことも主張しました。
ですが,高等裁判所は,形式的理由としては共用部分の変更に該当しないことを挙げつつ,実質的な理由として以下のように説明して組合員側の主張を退けました。
まず,特別の影響があることの立証責任は組合員側にあると指摘した上で,電磁波の影響等の健康被害が生じると認めるに足りる証拠がないし,漠然ととした不安感に過ぎないと判示したのです。
この高等裁判所の判断からすると,管理組合が賃貸できることは前提として,決議の要件を検討することになります。
また,特別の影響が争点になる場合には,組合員側で相当の立証を求められるものと思われますので,管理組合側も組合員も慎重な準備が必要になります。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (6)
- 2023年7月 (4)
- 2023年3月 (3)
- 2022年6月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (3)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (3)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (6)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (2)
- 2015年12月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年1月 (2)
- 2014年6月 (2)
- 2014年3月 (3)
- 2014年1月 (2)
- 2013年7月 (1)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (2)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (2)
- 2012年7月 (13)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (3)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (2)